生誕地の道標(松田駅)
松田駅前にある道標。

道標
二宮尊徳翁誕生地栢山道
約一里半
明治四十二年六月建之
約一里半
明治四十二年六月建之
周辺
道標の解説
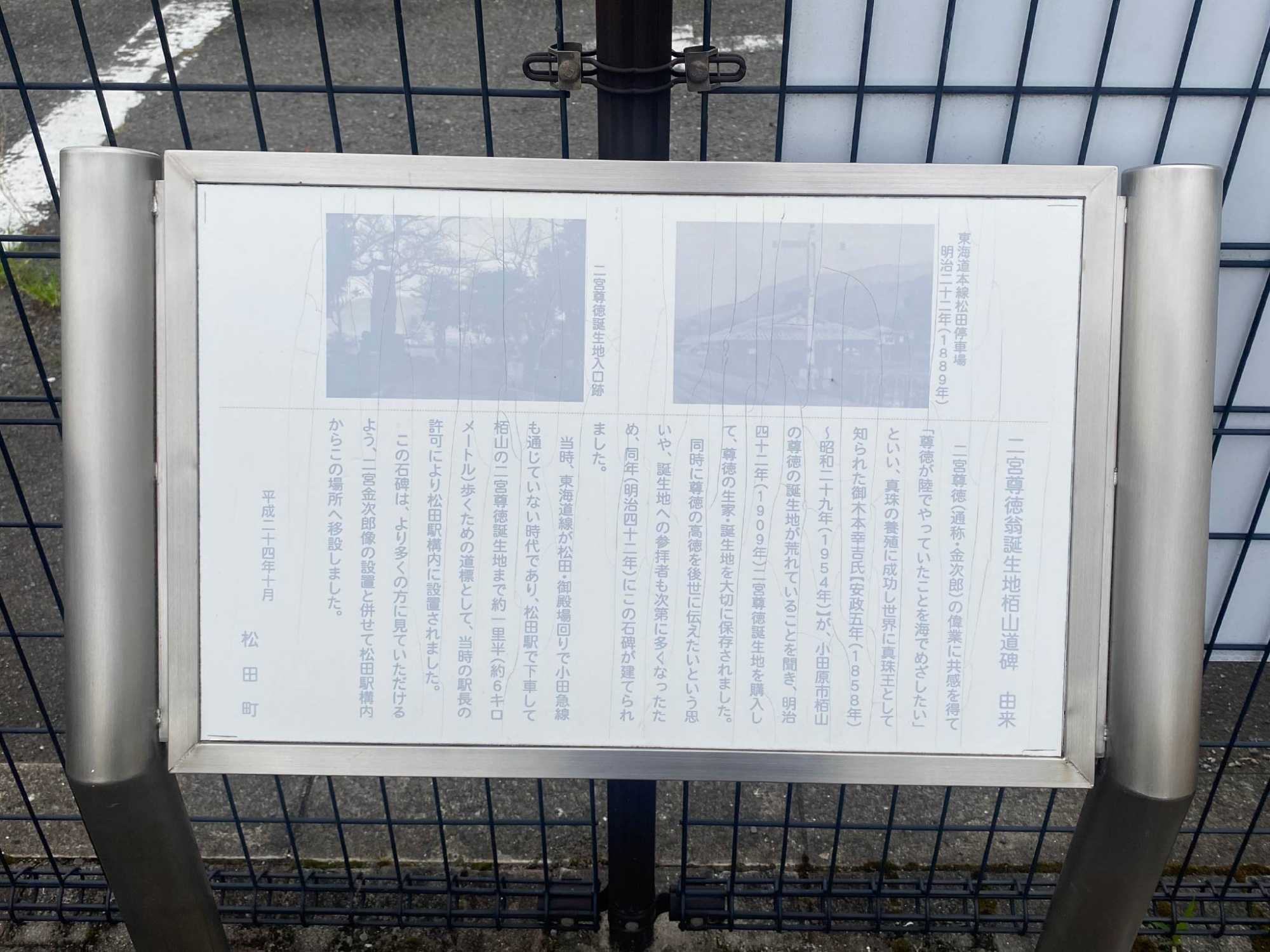
道標の解説
東海道本線松田停車場
明治二十二年(1889年)
二宮尊徳翁誕生地入口跡
二宮尊徳翁誕生地栢山道碑 由来
二宮尊徳(通称・金次郎)の偉業に共感を得て「尊徳が陸でやっていたことを海でめざしたい」といい、真珠の養殖に成功し世界に真珠王として知られた御木本幸吉氏【安静五年(1858年)〜昭和二十九年(1954年)】が、小田原市栢山の尊徳の誕生地が荒れていることを聞き、明治四十二年(1909年)二宮尊徳誕生地を購入して、尊徳の生家・誕生地を大切に保存されました。
同時に尊徳の高徳を後世に伝えたいという思いや、誕生地への参拝者も次第に多くなったため、同年(明治四十二年)にこの石碑が建てられました。
当時、東海道線が松田・御殿場回りで小田急線も通じていない時代であり、松田駅で下車して栢山の二宮尊徳誕生地まで約一里半(約6キロメートル)歩くための道標として、当時の駅長の許可により松田駅構内に設置されました。
この石碑は、より多くの方に見ていただけるよう、二宮金次郎像の設置と併せて松田駅構内からこの場所へ移設しました。
平成二十四年十月
松田町
明治二十二年(1889年)
二宮尊徳翁誕生地入口跡
二宮尊徳翁誕生地栢山道碑 由来
二宮尊徳(通称・金次郎)の偉業に共感を得て「尊徳が陸でやっていたことを海でめざしたい」といい、真珠の養殖に成功し世界に真珠王として知られた御木本幸吉氏【安静五年(1858年)〜昭和二十九年(1954年)】が、小田原市栢山の尊徳の誕生地が荒れていることを聞き、明治四十二年(1909年)二宮尊徳誕生地を購入して、尊徳の生家・誕生地を大切に保存されました。
同時に尊徳の高徳を後世に伝えたいという思いや、誕生地への参拝者も次第に多くなったため、同年(明治四十二年)にこの石碑が建てられました。
当時、東海道線が松田・御殿場回りで小田急線も通じていない時代であり、松田駅で下車して栢山の二宮尊徳誕生地まで約一里半(約6キロメートル)歩くための道標として、当時の駅長の許可により松田駅構内に設置されました。
この石碑は、より多くの方に見ていただけるよう、二宮金次郎像の設置と併せて松田駅構内からこの場所へ移設しました。
平成二十四年十月
松田町
二宮金次郎像

二宮金次郎像
二宮金次郎の解説
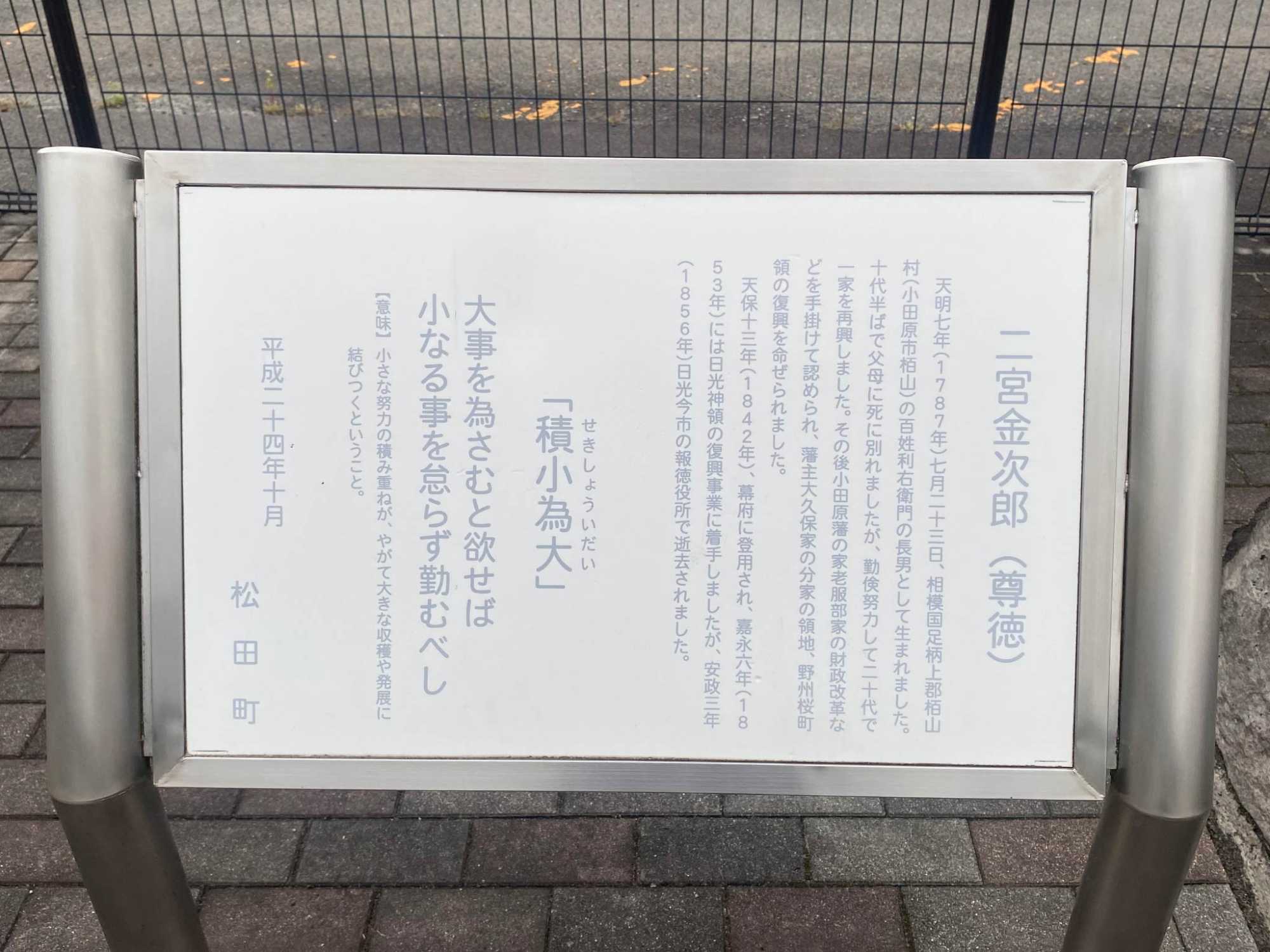
二宮金次郎の解説
二宮金次郎(尊徳)
天明七年(1787年)七月二十三日、相模国足柄上郡栢山村(小田原市栢山)の百姓利右衛門長男として生まれました。十代半ばで父母に死に別れましたが、勤倹努力して二十代で一家を再興しました。その後小田原藩の家老服部家の財政改革などを手掛けて認められ、藩主大久保家の分家の領地、野州桜町領の復興を命ぜられました。
天保十三年(1842年)、幕府に登用され、嘉永六年(1853年)には日光神領の復興事業に着手しましたが、安政三年(1856年)日光今市の報徳役所で逝去されました。
「積小為大」
大事を為さむと欲せば
小なることを怠らず勤むべし
【意味】小さな努力の積み重ねが、やがて大きな収穫や発展に結びつくということ。
平成二十四年十月
松田町
天明七年(1787年)七月二十三日、相模国足柄上郡栢山村(小田原市栢山)の百姓利右衛門長男として生まれました。十代半ばで父母に死に別れましたが、勤倹努力して二十代で一家を再興しました。その後小田原藩の家老服部家の財政改革などを手掛けて認められ、藩主大久保家の分家の領地、野州桜町領の復興を命ぜられました。
天保十三年(1842年)、幕府に登用され、嘉永六年(1853年)には日光神領の復興事業に着手しましたが、安政三年(1856年)日光今市の報徳役所で逝去されました。
「積小為大」
大事を為さむと欲せば
小なることを怠らず勤むべし
【意味】小さな努力の積み重ねが、やがて大きな収穫や発展に結びつくということ。
平成二十四年十月
松田町
