報徳仕法農家住宅
日光神領仕法時代の農家住宅。

報徳仕法農家住宅

報徳仕法農家住宅(内部)
周辺
解説
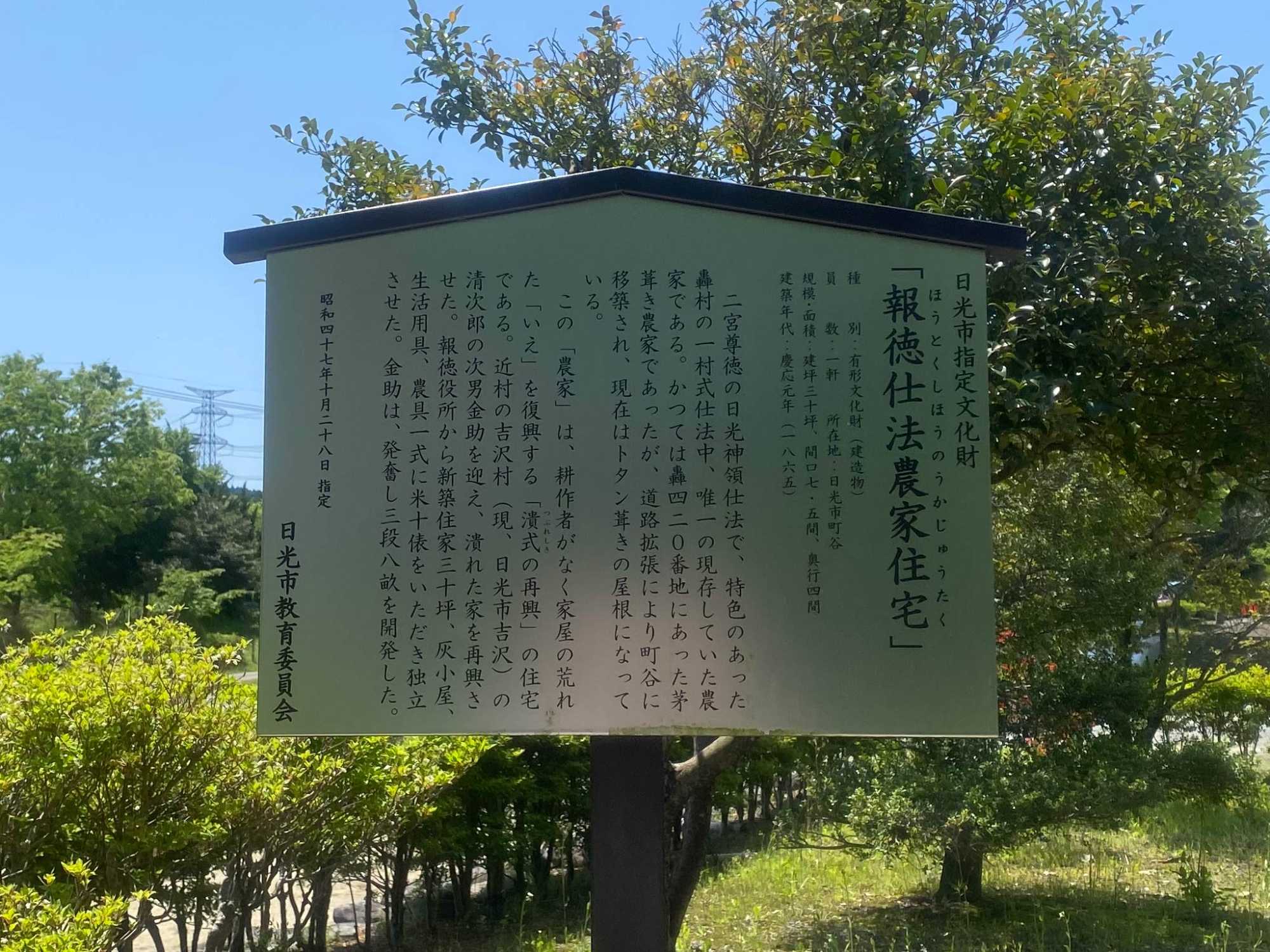
解説
日光市指定文化財
「報徳仕法農家住宅」
種別:有形文化財(建造物)
員数:一軒 所在地:日光市町谷
規模・面積:建坪三十坪、間口七・五間、奥行四間
建築年代・慶応元年(一八六五)
二宮尊徳の日光神領仕法で、特色のあった轟村の一村式仕法中、唯一の現存していた農家である。かつては轟四二〇番地にあった茅葺き農家であったが、道路拡張により町谷に移築され、現在はトタン葺きの屋根になっている。
この「農家」は、耕作者がなく家屋の荒れた「いえ」を復興する「潰式の再興」の住宅である。近村の吉沢村(現、日光市吉沢)の清次郎の次男金助を迎え、潰れた家を再興させた。報徳役所から新築住家三十坪、灰小屋、生活用具、農具一式に米十俵をいただき独立させた。金助は、発奮し三段八畝を開発した。
「報徳仕法農家住宅」
種別:有形文化財(建造物)
員数:一軒 所在地:日光市町谷
規模・面積:建坪三十坪、間口七・五間、奥行四間
建築年代・慶応元年(一八六五)
二宮尊徳の日光神領仕法で、特色のあった轟村の一村式仕法中、唯一の現存していた農家である。かつては轟四二〇番地にあった茅葺き農家であったが、道路拡張により町谷に移築され、現在はトタン葺きの屋根になっている。
この「農家」は、耕作者がなく家屋の荒れた「いえ」を復興する「潰式の再興」の住宅である。近村の吉沢村(現、日光市吉沢)の清次郎の次男金助を迎え、潰れた家を再興させた。報徳役所から新築住家三十坪、灰小屋、生活用具、農具一式に米十俵をいただき独立させた。金助は、発奮し三段八畝を開発した。
